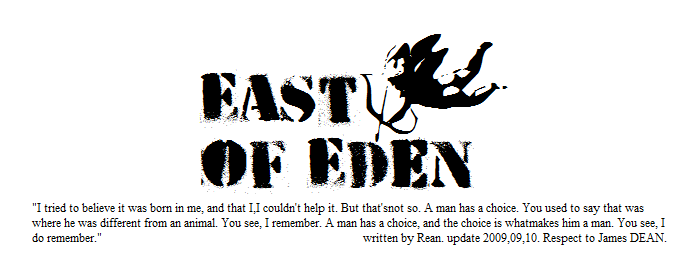エデンの東006>>
Half Years Later...
いつまでも、郭との電話のことで葛藤していられるほどの現実は甘くはなかった。
それからの半年は、呆然とする暇もないほど多忙でまさに忙殺という言葉を実感するほどめまぐるしいものであった。彼のことを考えている余裕すらないほどにあっという間に流れていく。なんとか就職先も決まり、活動の拠点がいよいよ都心に移ることが嫌でもこの先の未来に近づけていく。卒業論文の内容も三年次からの構想通りに形作られ、あとはアンケート調査や細かい統計などを出すのみとなった。教授の資料室で先行研究などを漁りながら同時に広げたものの整理に時間を費やしていると、穏やかな声がかかる。
「さん、ここにお茶おいておくから飲んでね」
「すいません、教授。資料室使わせていただいているのに、ご迷惑をおかけしてしまって・・・」
「いや、いいんだよ。今そのお茶消費するのに必死でね、気に入ったらたくさん飲んでくれて構わないから」
「ん、なんか変わった色のお茶ですね」
渡されたカップの中身を覗き込んで、は目を丸くする。
お茶、というよりもレモネードのような色をしている。レモンピールかオレンジピールのようなものがぷかぷかと浮いていて、ジャムを説いたような酸味のある味が口に広がる。
おっかなびっくり、口にするの様子がよほど面白かったのか、教授は声を上げて笑いながら教えてくれる。
「柚子茶っていうんだよ。韓国の飲み物でね。春休みの間に妻の実家に寄った際に出されたんだがこれがまた美味しくて、素直に褒めたら二キロ分も貰ってしまって・・・。毎日飲むわけじゃないからね、こうやって細々消費してるっていうわけさ」
「はぁ、」
飲み方の作法などは全くと言っていいほどわからないが、とりあえず渡されたマドラーで柚子のピールを軽く口に含んでみる。
甘酸っぱい香りが口に広がり、教授が美味しいという理由もわかる。日本でお茶と称するほどの苦味はなく、どちらかといえばロシアンティーの部類に入るのだろうか。
「時にさん、うちの英士と何かあった?」
「な、なんですか。藪から棒に!」
思わず過剰反応を決めてしまう自分はもはやどうかしているのか。は肺に入りかけた柚子茶をなんとか飲み込み、教授に応じる。
教授はといえば、いつものように柔和な顔でこちらを見ている。息子を誑かした悪魔とでも思われているんだろうかとは縮こまりたくなる。
「いや、うちの息子が半年前くらいから、こっちに戻ってこなくなったんだ。それに、君もうちに遊びに来なくなった。別にもう二十五だし、いい加減いい大人なわけだからそれもありかと思ったんだけど、君も揃って来ないだなんて、それにしたって何かあっただろうって思って代表が決まったって聞いた時に少しカマかけてみたんだ。そしたら君と何かあったみたいな雰囲気だからさ、気になってね」
「何かって、誤解を招いてらっしゃるみたいですからはっきり言いますけど・・・付き合ってすらいないですよ」
「うん、だろうね。うちのはさ、なんていうか一にサッカー、二にサッカーで生きてきたもんだから、女性関係がからっきしでね。人間関係のハードルが無意識に上がっちゃってんの」
自分の息子のこととはいえども、そこまであけすけに言っていいものなのだろうか。がいぶかしむ気配がわかっていても、教授は話をやめる気配はないようだった。
それどころか、はいつもの癖で、気になったことを思わず尋ねてしまう。
「ハードルって何ですか?」
「サッカーをプロになるまで追い続けてきたからかもしれないんだけど、自分に厳しいから無意識に他人にも厳しさを求めてるんだよ」
ああ、だから―・・・。
教授の言葉で、は郭の言っていた境界の話が少しだけわかってきた。けれども自覚している節があったのか、あの時はに押し付けるような真似はしたくないと言っていた。
彼だってとうに承知しているだろうに、自分の中にある実直さが手を抜くことを許さないのか。は僅かに微笑んだ。中学・高校と生きてきた中で経験していることだった。
「あれですね、テストは絶対八十点以上タイプですね」
「お、よくわかってるじゃないか」
「私とは正反対だから、逆によくわかるんです」
「うーん、君は割となんでも要領よくこなしそうだからね、ハードルが低いのではなくそもそもないんだ」
「そうかもしれません。私、器用貧乏なんです」
「器用貧乏も才能のうちだよ。そんなさんだから、うちの息子なんかにひっかかっちゃうんだろうねぇ」
「それは、ちょっと違います。引っかかったのは私の意思です」
「だそうだよ、英士」
突然湧いた名前にが目を通していた資料から顔を上げると、教授が親指で示す先―・・・研究室のドアの側には、かつて教授を迎えにきた時のように、郭が寄りかかって立っていた。
いつものようにジーンズと黒を基調とした服で、きっと伊達だろうが眼鏡までかけて、より四つも年上なのに大学生に溶け込んで見えるのが不思議だった。
状況が全く飲み込めないは助けを求めるように教授を見れば、彼は彼でしてやったりという表情で悪戯っ子のように笑んだ。
「英士はともかくさんがうちに来ないのを妻がひどく寂しがってね。ちょっとは不詳の息子の話を聞いてやってくれないか?」
「そんな、私は・・・」
― 彼のことをきっと傷つけているのに、
出かかった言葉は容易く呑み込まれ、繋ぎ合せようとした言葉すら見つからないまま閉口するしかない。
「おっと、僕はこれから授業だからこれで失礼するよ。ああさん、カップはそのままで構わないから」
そう言って、コピーした用紙の山と名簿を持って、教授は郭の脇をすり抜けて研究棟から消えていく。
遠ざかっていく後姿を見つめて、は資料を綴じながら視線を彷徨わせた。辿りついたのは彼が片手に持っていた文庫本だ。
文庫本はありがとうという言葉とともに差し出されるまま、そっけなく受け取ると、資料と共に鞄の中に詰め込んだ。
「ちゃん、こっち見て」
胸が痛い。―・・・どうして。
「ごめんね、こんなことして呼びとめて」
「なんで―・・・」
「なんで今って? 就職活動とかある時期に余計な思いさせるのはどうかと思ってね」
タイミングを見計らったら四年生になってからだと思って。けどあまり学校に来ないって言うじゃない。それで待ち伏せすることにしたんだ。と悪戯が成功した子供のような笑みを浮かべて彼は笑う。
「・・・どうしてそんな、私なんかを大事にしてくれるんですか」
「君が俺のことを大事にしてくれようとしたみたいに、俺も誠意で返したいと思った。理由になってる?」
鞄の片隅の携帯電話を見つめ、は半年前に彼にとんでもない言葉たちを浴びせてしまったとすぐさま顔を上げた。
「私がしたことは誠意じゃないです!・・・私あんな酷いこと言ってしまって」
「もう時効だよ。気にしないで。ここじゃ難だし、仲直りのためにゆっくり話したいんだけど、どこかいい場所知ってる?」
年の功か、いつも郭の調子に巻き込まれてばかりだ。はいつものように穏やかな表情を崩さない彼を見つめ、
それから問いかけられた言葉の真意を探るように額に手を宛てて表情を崩し、ややあって頷いた。
「とっておきのところがあります」

「むしろ嬉しかったよ。あの時真っすぐに気持ちをぶつけてもらえて、だから半年の間、俺もゆっくり考えてみたんだ。父さんたちについて久しぶりに韓国にも行ってみた。やっぱり、あの国は俺の居場所じゃないと思ったけど、同じ時期に帰ってきてた従兄の顔を見てあの国には大事な奴もいるんだって改めて気がついたよ」
そう言って郭は微笑する。そんな風にすっきりした心地で笑う彼をは初めて見た。
二人きりになるには丁度良い、親しい友人とよく訪れていたイタリアンバールの片隅で。指先で摘まんだカクテルが波打つのと同様に、郭の声がの心を波立たせていく。
静かな空間だが、今日はたまたまイタリアからのサッカー中継をしているのか、店内は外国人の客と日本人の客、両方で溢れかえっていた。
その中には勿論、郭のことを画面越しに見知っている者もいたことだろうが、アルコールの酩酊感と中継に夢中の客の殆どが彼の姿に気がつくことはない。
「だから、気がついたんだ。前に言ってたでしょ、ちゃんの居場所が俺の中のどこにあるのかって」
「あれは―・・・言葉の綾みたいなもので、」
「いや、聞いてよ。俺は最初に会ったとき、一から関係を築いていくみたいな感じがすごく心地よかったんだ。だから、俺はあの電話で終わりにしたくないと思った」
手放したくないんだ。と、郭から添えられる言葉たちとお気に入りのマンハッタンが、の心を溶かしてしまう。甘くてほろ苦い味わいが頭の芯すら痺れさせる。
かき口説かれるように語られるよりも、半年ものことを慮って行動を起こさないでいてくれたのが何よりも雄弁に伝えてくれる。
全てが本気だとは彼の眼差しを受けて悟る。前に一緒に食事をした時もそうだった。彼は本当の言葉をくれる。それだったら、偽りなく気持ちをぶつけたくなる。
はグラスから指先を話して掌をぎゅっと握りしめた。どうしようもなく、郭のことが好きだった。今更なことなのに本人を前にして向き合うとちゃんと言えない。
電話越しならば、あれほど簡単に大嫌いも大好きも、出てくるのに・・・。熱っぽくなった頬を片手で押えて、は目を伏せた。
「私、すごく後悔しました。忘れてほしいなんて嘘です」
「謝らなくていいよ」
「ううん、私が謝りたかった・・・。怖かったんです。急にあなたが遠ざかっていく感じがして。遠ざけたのは自分なのに」
「サッカーしてる俺ごと好きになってもらえたら、それこそ贅沢だ」
力の籠もったの指先を解すように優しく触れて、よりも大きな掌を重ねて囁いてくれる。急ぐ必要は何もなかった。
彼の掌の温度が、心地よく、は彼にしか聞こえないくらいささやかな声で半年前に告げそびれた言葉を唇に乗せた。
「ありがとう、郭さん。私、あなたのことが大好きよ」
「ホントは、俺が先に言うはずだったんだけど」
それに、その郭さんっていうのそろそろやめにしない。と郭は悪戯っぽく笑う。いつもの笑い方だ。
額を寄せてひとしきり笑いあったところで、ふいに郭の指先がの髪をあやすようにして触れた。その手つきはいつくしむように優しい。
柔らかなベージュの唇に指先が辿ったところで、彼は問う。
「キスしても?」
はわざとらしく、はいもいいえも言わない。許可を求めているわけではないことくらいわかる。バールの視線は中継中のサッカーに夢中だ。
そして、そんな人の目を掻い潜るのは造作もないことだろう。
瞳があったのを合図にして待ちかねたようにが瞳を閉じれば、郭がそっと顔を傾けるのがわかった。二人の距離がゼロになるまであと―・・・。
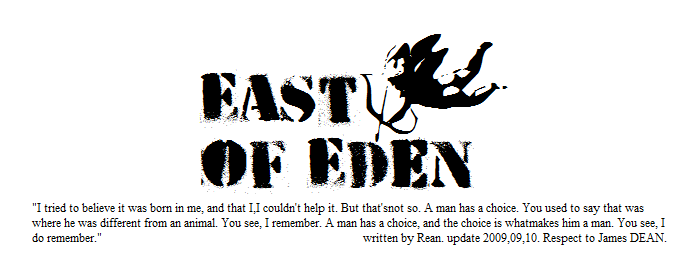
![]()