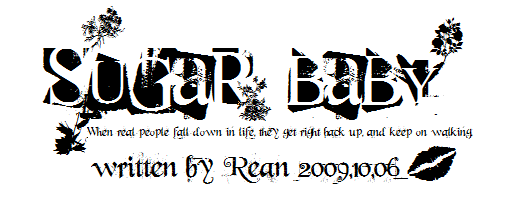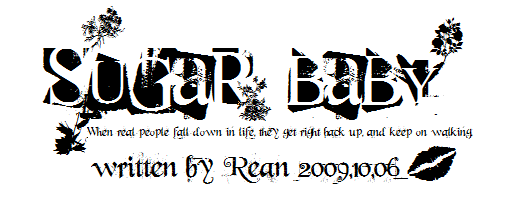シュガー・ベイビー:Sugar Baby
「はい、これ」
の目の前に差し出された黒い箱は艶やかに濡れたような色をしていた。
黒い箱に金の縁取りで一見して高価そうに見えるその品物に思わず顔を上げて、目の前に経つ従兄の顔を見上げながらは問う。
「平馬くん、これなに?」
「ん・・・遠征土産」
気のない雰囲気で、の従兄―・・・横山平馬はの手にその箱を押し付けるようにして握らせてくる。
その手が意外と大きく、有無を言わせない力を持っていたことには酷く驚いた。あれ、平馬くんの手ってこんなに大きかった?
の内心とは裏腹に、一通りの動作に満足したのか、彼は傍らにあったテレビゲームに集中し始めた。
完全に置いてきぼりをくらったはただ手の中にある箱と従兄を見比べながら、お礼を云いそびれたことを思い出した。「あのぅ、」声にすると、彼は思い出したように振り返る。
「気が向いたら使って」
「・・・うん? ありがとう」
何の事だかわからずに、は中身も開けずに曖昧な返事を返す。それは、母方の実家である静岡に帰省した夏の日のことだった。
静岡に住んでいる従兄から、海外遠征のお土産だと云われて貰った小さなケースには柔らかな色をした口紅が入っていた。
銀座の路面にある有名なブランドのマークが刻印されたケースは、どう見ても中学生であったには身分不相応だ。
かといって、それを男である従兄に突き返すわけにもいかず、ましてや母に横流しするのもどうかと思い結局机の引き出しの中に仕舞い込んだ。
化粧に興味がなかったわけではない。だがはどちらかというと野生児で、家の中にいるよりも公園をかけずり回っているような子供だった。
けれどもそれすら忘れるほどに、はその色に魅入った。なんて綺麗な色。
直接塗ろうと鏡を片手にしながら口元に持って行ったところで急につけることが躊躇われて、結局口紅をケースに仕舞い込んだ。勿体ない。
なぜだろう。彼はなんで、こんな物を贈ってきたのだろう。
***
―・・・きっと、もっと早く訊いておくべきことだったのかもしれない。
目の前に置かれたマルガリータのグラスを見ながらはそんなことを考えた。
大学に入って、彼氏もできて、それなりに順調な日々を送っているにとってもはや従兄の贈り物のことなど忘れておくべきもののはずだった。
行きつけのコスメカウンターに足を運ぶたびに交通事故のようにあのブランドの表象と出会ってしまう。そのたびにはふと思い出す。なんてことだ!
大人になった今となってはシラフでは、そんな思い出話を聞けやしない。今になっても覚えている自分の頭が痛すぎる。
せめてお互い酒が入って、なんとなく思い出話をするような時にふと零れ落ちるべき話だ。
だが残念なことに酒の席すら共にするなんてことは殆どない。むしろ、なきに等しい。異性の従兄というのは思春期を超えてしまうと酷く細い糸でしか繋がりを持たない。
しかも彼は日本代表にも選出されるサッカー選手である。ただでさえ細い糸は更に細くなっていく。
連絡がつかないわけではない。携帯電話のメモリーにはなぜか彼のアドレスと番号がしっかりと収まっている。
その上、よく買うファッション雑誌に彼の姿が取り上げられることがしばしばある。どちらかといえば同世代の選手である山口や須釜の方が女性誌向きではあるが、彼らとの対談や交流がある幾人かの選手との対談もほんの少しの枠に載っていることがある
のだ。
雑誌で見る従兄は、の知る横山平馬の姿とは少し、いやだいぶ異なっている。
ぼんやりとしていないし、快活だし、いつもはぽつりぽつりと零すようにしか話をしないのに真剣に受け答えしている。
だが、たまに試合に勝った興奮からか、饒舌なメールを彼からメールを寄こしてくることはある。けれどもから話すべき理由がない。
試合勝ったね? おめでとう? 代表頑張ってね? 思いつくものはどれも陳腐だ。
グラスの淵できらきらと光る塩のかけらを摘まんで悪戯にグラスに落としながら、は小さく溜息をついた。
「口紅ねぇ、それって少しずつ返してって意味があるらしいよ」
目の前でカクテルを作ってくれる友人が、の疑問に意味深な答えを呈してくる。
彼女の上がりの時間はとうに過ぎているらしく店長の許可を受けてこうして一緒に飲んでいたのだが、少し酔っているのかほんのりと染まった頬を片手で押さえながら彼女は笑った。
「返す?」
「いやだ、言わせないでよ」
「え? 何、いいじゃん教えてよ」
「いやーそんな、言えませんわー!」
「はいはい、帰って調べますよ」
「でもそんなことするなんてフランスの映画みたいね。の彼氏ってばロマンチック!」
「あー・・・そうなの?」
独りで盛り上がってしまっている映画通の友人を尻目には彼氏ではなく従兄なのだがと訂正を入れるのをすっかり忘れてしまっていた。
「の彼氏いいじゃん! 法学部なんでしょ? 捕まえとくべきだよ」
確かに、の彼氏は法科大学院の学生だ。将来弁護士になると躍起になってお勉強とサークルにいそしんでいる。
対するは理系の学生だ。実験と分析、レポートに追われる日々。専攻の分野や学部が違うと確約しておかない限りには、キャンパスで顔を合わせる機会が滅多にない。
「でも忙しいんだって、週に一回レポート出さなきゃいけないから会えないってそればっかり」
「まぁ文系の大変さは理系にはわからないもんね。逆も同じだけど!」
「そうなんだよねぇ・・・でもどう思う? 私忙しいを言い訳にして会ってくれない人とこれ以上付き合ってく自信ないよ」
「そりゃ辛いね。遊びって割り切れないと傷つくね」
恋愛経験の豊富な友人はいつでも切れ味のよい答えをくれる。だが、はいつだって一瞬でも先のことを意識してしまう。
「私、大事にされてたいのかなぁ・・・」
「ってマメな男が好きなわけ?」
「そういうわけでもないの。ただ・・・ごめん、上手く言えないや」
「不満があるなら云うべきだと思うけど」
「私、我儘になれないんだと思う。あと家族に大事にされすぎたわ」
に反省点があるとすれば思いつく限りはその二点だった。
両親はにこれ以上にないほど愛情を注いでくれたしお金もかけてくれた。現に大学にも行かせてくれている。
融通が利かないとすれば二十歳まで設定されていた門限くらいなもので、あとはそれなりに自由だった。
我儘になれないのは、与えられることに慣れてしまっているからなのか。それとも、手の届かないものに無意識に引いてしまっているからなのか。
分析しようとすればするほどに首を傾げるばかりになるは、グラスに残ったアルコールを飲み干した。
舌先を柔らかく痺れさせる刺激に唇を拭うと、友人がもう一杯どうかとグラスを示す。は頬を緩めて首を振った。
「あ、もう十分・・・てかかなり回ってきたからそろそろ帰るわ」
「じゃあ片づけるよ。駅まで一緒に帰ろう」
「うん。じゃあ待ってる」
別口で会計を済ませて、は友人を待った。従業員の出入りする裏口。
締め切られた黒塗りの扉からひょっこりと姿を現す友人と連れ立って、ネオンの煌めく街並みを歩く。
時間短縮だと言って隣の友人がディオールのポーチから煙草を取り出して歩きながら火をつける。
歩き煙草は基本的にはしない主義のようだが、たまに感覚が麻痺して彼女はこうして吸っている。一応、つかまっても知らないけどとおどけたように言っておいた。
その矢先。
「、ストップ」
駅に続く道のりの手前、友人が小声で鋭くを制した。腕を強く掴まれたせいで一瞬前のめりになっただが、目の前に現れた光景に時が止まった。
「・・・え?」
「ちょっとあれ、あんたの彼氏じゃないの?」
「う、そ・・・えっ!?」
酔いが回った効果もあってか、は思わず目をこすった。残念なことに、目の前の光景は幻でもなく、何一つとして変わらない現実だとに示していた。
ここでがっくりと膝でもつけたらドラマティックだろうが、あいにくとは棒を呑んだように立ち尽くすだけで視線は目の前の男女から離れてくれはしなかった。
横顔、目元、着ている服装、どれをとっても見覚えがある。間違いなくの彼氏である。だが隣にいる女性には見覚えがなかった。
友人かもという言葉が思いつかなかったのは、二人が仲良く腕をからめて休憩所と名のついたラブホテルからご登場なさったからである。
心配そうにを見つめる友人を尻目には思わず額に手を宛ててしゃがみこみ、無意識に呟いていた。
「・・・終わった」
***
衝撃はどちらかといえばあとからやってきた。
ボディーブローを喰らった後のように駅の近くで見た光景はじわじわとの心に不吉な影を落としてきた。
電車に乗ってから家に帰るまでの間に、腹立たしいやら不甲斐ないやらの心地になり、心が掻きむしられたようだ。多分疵口に喩えるなら滅多刺しで失血死寸前。おまけに
飲酒の酔いが回ってきたのか胸の奥が重い。だがアルコールの所為のみではないことをはよくわかっていた。
「・・・むかつく、何あいつ、ばかじゃないの、サイテーでしょ!」
帰宅して、湯船に浸かったあたりで苛立ちは最高潮になった。浴槽に身を沈めながらは彼を呪った。
それだけではない。なぜそんな不埒者だと見抜けなかったのか、自分の眼力すらも呪った。
「あんなのと、付き合った私が一番馬鹿!」
風呂場で怒鳴り声を上げると、悶々とした気持ちが反響する。馬鹿馬鹿馬鹿馬鹿、ばか、ばか、ばか、ばか!湯船を叩いて暴れるに、脱衣所から「もう深夜よ。静かになさい」と母から小声で説教を喰らった。
大人になっても親に注意されるだなんて、これも最悪だ。もまた声を落として謝りながらまた、湯船にもぐりこんで吐息で柔らかく泡を立てた。
頭を冷やせとは言うが湯船のおかげで温まる。
悲しみよりも、なぜか悔しさが勝ってか、涙は不思議と出なかった。
***
理性ではわかっているというのに、感情に蓋ができない。
ぼんやりとした瞬間や独りになった時に必ずと言っていいほどに深夜の光景がよぎる。三週間くらい経っているのに雑念が払えないとは何事だろうか。
はそれこそ毎日、余分なことを考える時間が生まれないように忙しさに身を浸してきた。
実験に、勉強に、バイトに、遊び―・・・勤しみ過ぎて家に帰る頃にはもう泥のように眠る日々だ。ありがたいことに夢には出てこない。
ごろごろとベッドに寝転び、まどろみかけたところで、部屋をノックする音に飛び起きた。
「な、なに?」
「? 平馬くんから電話よ」
扉を開けると、母が子機を片手に立っている。
差し出された子機をそっと受け取りながら首を傾げていると、母は悪戯っぽい笑みを浮かべて笑う。
「あんたの携帯にかけたけどつながらなかったって、いつの間に交換してたの?」
「おばあちゃんの法事で静岡行った時」
「ふぅん。じゃあ、ごゆっくりー」
「そんなんじゃないってば! 母さん!」
彼女なりに空気を読んでか、階段を下りて消えていく後ろ姿に追いすがるように声をかけたが無意味だった。
去っていく後姿に溜息を漏らして部屋に引っ込むとは電話を取った。久しぶりに電話越しに聞く平馬の声だ。
『今平気か?』
「うん、っていうか久しぶり。元気?」
『まぁな。お前は? なんか元気ないけど・・・』
「だ、大丈夫! ちょっと私寝かけててさ、」
胸を突くものがあったが、は誤魔化すように声を上げた。正直、かなり重症である。
だが、平馬は興味がないのか、気付かないふりをしてくれているのか、悪かったなと呟きながら話を続けてくれる。
『実はさ、明日から明後日まで遠征で東京に行くんだ』
「うん」
『あのさ、試合が終わった後メシ食いに行かないか?』
従兄との食事を断る謂れもなく、は曖昧に頷いていた。
「うん・・・。私はいいけど、平馬くんは大丈夫なの?」
『大丈夫って・・・何が?』
「その、彼女とか、週刊誌とか」
『別にいいし、云わせときゃいいよ。てか彼女いないし』
「あ、そう」
なぜ彼女の有無を確かめる質問なんてしているのか、は行動の選択を誤ったと内心舌打ちをした。
ふと、視線を泳がせたところで件の机の引き出しが目に入り、は思わず呟いた。
「あのさ、」
『ん?』
「いや、なんでもない。ごめん、こっちの話」
『あ、そ。じゃあ明後日の・・・っていうか、どこがいい?』
「えぇ? 行きたいところとかないの?」
『だって俺の地元じゃないし。詳しくない』
―・・・もっともだ。
「じゃあ、私調べとくから、平馬くんは試合頑張って」
『うん、任せた。詳しくメールくれると嬉しい』
「うん、任せて・・・」
頷きながら、じゃあまた、と呟いて電話を切った。
慌てて荷物を漁り、携帯電話を取り出すが画面は真っ黒で電池切れを報せていた。
思わず呆れかえりながらは充電器に電話を立てかけると、今度は部屋を出て、子機を居間に戻しに階段を降りはじめた。
親機の隣に子機を並べたところで、目の前に立てかけてあるカレンダーに食事の予定を書き込みながらは思わず手を止めた。
―・・・あれ、これってデート?
にしては、セッティングをする立場が逆である。
***
そして、その日はやってきた。
平馬にしてみれば、何気なく従妹を誘ってくれた電話だったのだろうが、
にしてみれば彼氏―もう元彼と云うべきなんだろうか―との今後を考えなくてはならない時間が減って助かった。
文句を言うのにも疲れるし、今更もうどうにかなりたいと思うわけではなかった。連絡は何度かあったがそのたびに気のない返事を返すだけだ。
もう彼と同じベッドに入りたいとは思わないし、抱きしめてほしいとも、キスをして欲しいとも思わなかった。彼の言い訳も聞きたくなかった。
その代わりとばかりに、は平馬のことを考えてしまい、こちらもどうしようもなく落ち込む。
こんな、彼氏の浮気現場を見た後に平然と他の男と食事に行くなんて自分の神経の太さに驚いてしまう反面、同じことをしているのではないかと悩んでしまう。
これって浮気なのだろうかとか、テレビや雑誌のインタビュー記事でしか殆ど見ることがなくなった彼の姿にどうしたらいいものかと、そればかりだ。
は腕にしているシルバーの時計を眺めながら平馬を待った。
祖母の法事の時に会っているとはいえ、直に会うのは恐らくだいたい二年ぶりである。
が気持ちを落ち着けるように胸元に手をあてて吐息を漏らしたところで、の足元を覆ってしまう長い影ができる。
おや、と顔を上げたところで少し猫背の彼と視線が絡まった。平馬だ。
「待ったか?」
「ううん、大丈夫。それよりよかった、ちゃんと会えて」
電車に乗ってやってきたことがそもそも意外では驚いたが、彼の格好を思わず上から下まで見て、はまた驚いた。そういえば、ジャージではない。
今日の彼は普段着というには少しお洒落なジャケットとシャツに濃い色のデニムだ。おまけに顔には眼鏡がついている。至ってシンプル。出かける時はこんな格好するのか。
の視線の意味に気がついたのか、平馬は相変わらず表情を変えないままで、けれども邪魔になったのか眼鏡をとると、首の後ろを小さく掻いた。
「変?」
「いや、全然・・・ていうかちゃんとした格好してるの見るの法事以来だったから」
「俺だってジャージ以外の服くらいちゃんと持ってるし」
「そりゃわかるって」
は自然と口元を緩めて笑った。自分がこんなにも自然に笑えていることに驚いた。
「あ、よかった。笑った」
「え?」
「なんか、元気なかったみたいだし」
そう言って平馬は、自然との手を掴んだ。指先すらすっぽりと包んでしまう大きな手は彼を男と認識させるには十分だった。
恋人に裏切られて傷心している最中だと云うのに、には薬どころかもはや毒だ。優しくしてくれる彼に何もかも許してしまいそうで怖くなる。
「嫌だったか?」
「ううん・・・嫌じゃない」
は頷きながら、恥ずかしげに俯いた。これではまるで、彼と恋人のようである。
「店どっち?」
「平馬くんが何を食べたいのかわからなかったから、勝手に選んじゃったんだけどよかった?」
「肉以外なら大丈夫」
「あ、ならよかった」
はほっと胸を撫で下ろした。予約をとっていた目黒のダイニングバーで大丈夫そうだ。
芸能人並みに有名になってしまった彼と行く店を探すのは少し気合いが必要だったが、成人した折に家族で訪れたそこが酷く印象に残っていては今回彼との食事の場所として選んだ。
見た目はまさしく普通の民家なのだが、ガレージを抜けて中に入ると内装は落ち着いた雰囲気を織りなしている。
静かな彼と来るにはうってつけの場所だった。
「平馬くんお酒飲む?」
「いや、俺そんなに飲めないから」
「あ、そうなの? それは残念」
は相手に合わせて酒を嗜むのが好きなので飲まないと云われれば躊躇わずに手を止められる。
だが平馬は自分の傍らに置かれていたアルコールのメニューをに差し出す。
「でも、やなことでもあったんだろ? 好きなだけ飲めよ」
「うん・・・っていうか、なんでわかるの?」
「ん? 何が?」
「嫌なことがあった・・・って」
「見たり、聞いたりすればわかる」
電話の声音だけで元気がないことがわかったり、こうして会った時に自然と優しくしてくれる彼がなぜ恋人ではないのだろう。
なぜ、裏切られなければならなかったのだろう。非があったのなら躊躇わずに言って欲しかった。
ごめんの一言もなかったことへの苛立ち、嘘をついてまで付き合ってほしいとは思っていなかったこと。様々だ。
平馬はただの唇から零れる不満に相槌を打ちながら運ばれてくる料理をマイペースに口に運んでいる。
そんな彼を自分の愚痴に付き合わせているのが申し訳なかった。は何度か平馬に謝りながら瞼から零れ落ちてくる涙を拭った。
悲しさより悔しさが強かったのも本当だが、本当は早くに泣いてしまいたかったのだ。
ほどよく注がれたワインを飲み干しながら、は少しだけ渇いていた何かが潤って、心が軽くなるのを感じていた。
***
駅ビルの中で、知り合いへのお土産にお菓子を見ていくからと言われたので、
は先に地下鉄の改札に直通のエレベーターに乗り込もうとボタンを押してドアが開いたところで固まった。相手もしかり。
「あ、」
「えっ」
エレベーターを開けて運悪く、は今この世で一番会いたくない相手と遭遇した。
駅の作りに合わせた重厚なデザインだが、設計上のミスか監視カメラのない密室のエレベーター。彼と自分だけが乗っているのをいいことに、は口を開いた。
「一か月前のラブホ、楽しかった?」
の際どい台詞にぎょっとしたように目を剥くと、彼は持っていた携帯電話を取り落としそうなほどにおののいた。扉が閉まる。
「いや、あれは・・・彼女が」
「嘘を吐くことは別に悪くないわ、嘘も方便って言葉があるし。でもあなたがやったことは違うでしょ!」
「、落ち着いて、俺は・・・」
「そんなにお勉強してるくせに、ごめんなさいも言えないの!?」
は履いていたピンヒールを脱いで、男に向かって投げつけた。
怯んだ男に詰めよって胸倉を掴む。女の力では簡単に振りほどかれるが、バッグも壁に放り投げて、徹底的に揉み合った。
こういう時は野生児だった頃の血が騒ぐ。が男を殴った拍子に元彼の顔から鼻血が出た。ざまぁみろ!
二人がここがどこだか忘れかけている頃に、どこかの階への到着を報せる音がした。ぎょっとしては振り返る。
その拍子に男の方が床にしゃがみ込み、わざとらしく鼻を押さえた。なんという素早さ。
ほとんど無傷のと、鼻血を出している男。明らかにの方に非がありそうな光景である。
「あ、」
「へ、いま、く・・・」
平馬は何食わぬ顔でエレベーターに入ってくると、無言で《閉》のボタンを押しこんだ。
彼のオーダーに応えるようにすぐに閉まるドア。それを尻目に彼はの手を掴んで男の胸倉からはずさせると、顎をしゃくって男を見た。
「これが、元彼?」
「そうよ」
そう言ったが早いか、突然平馬はの髪をぐしゃぐしゃに掻きまわした。
映画かドラマならあちらを一発殴りに出るところだろうに、何をしようとしているのかまるで分らずは先ほどの昂った感情のままに叫んだ。
「へ、平馬くん!? 何して・・・」
「いいから、」
そしていきなりスカートの裾を掴んで引っ張る。新しく買ったグレースコンチネンタルのスカートが平馬の手にかかってしまえば哀れなほどに布切れになる。
これには鼻血を出している男の方が座り込んだまま呆気にとられている。
「何!? 一体何なの!? ちょっと、ねぇこれ高かったんだよ!?」
「新しいの買ってやる」
「なにを・・・」
これじゃまるでセックスの最中の会話だ。だが場所が場所で、酔った勢いにしては醜悪すぎる。何が起きているのか判らずは今にも泣きだしてしまいそうだった。
この密室にいる誰もが《開》のボタンを押さなかったが、再び扉が開いた。外から押されたのだろう。
その瞬間、殆ど反射的に平馬はの肩を守るようにして抱き、落ちていたバッグと靴を掴んで外に出ながらわざとらしく言った。
「こんなひらひらしたスカートで外に出るなって言ったろ!」
だから狙われるんだ。無事でよかった。どうなるかと思った。すぐに帰ろう。
自分でやっておいて、どこからそんな言葉が出るのか。は平馬の腕に支えられながら呆然として彼を見た。
オフィス街の終業にほど近い時刻だったためか、駅ビルの利用者が多く、エレベーターの外には小さな人だかりが出来ていた。
エレベーターから出てきたぼろぼろの若い女とそれを支える男、エレベーターに取り残された鼻血を出して座り込んだ男。
どこから見ても、暴漢とその被害者である。いきなり立場が逆転し、は平馬が男を殴らなくて本当に良かったと心から思った。
手は出していない。殴ったのはだ。もしも横山平馬だと知ったなら、あの男は変な難癖をつけてくるに違いない。
が今更ながら安堵していると、傍らの平馬がの肩を強く引き寄せて囁いた。その仕草にすら胸が高鳴る。こんな状況なのにどきどきするなんてどうかしている。
「お前を騙してた分の制裁は十分に受けたろ」
「やりすぎだよ。特にスカート」
「・・・ごめんなさい」
素直に謝ってくる平馬の落ち着いた声には視線で返しながらぼろぼろになってしまったスカートを見つめて苦く笑った。
「いいよもう。スカート一つで仕返しできたなら十分。でももう心臓に悪いからしないで」
「ああ、次はないし」
「まぁ確かに、あの人ともう会うこともないだろうし・・・」
「ホント鈍いな、相変わらずだけど」
不意に零された一言には思わず大きく目を開いて、平馬のことを凝視しなければならなかった。
「ね、どういうこと? 相変わらずって・・・」
「シャネルの口紅」
「あっ、えっ?」
「やっぱ、わかってなかったか・・・」
少し落胆したように肩を落としたのがわかった。は縋るように平馬の腕を掴みながら問う。今なら聞けそうだった。
「ねぇ、あれ何の意味があったの?」
「ん、こういう意味」
突然、頭の後ろを抱くように平馬の指で包まれたかと思うと、目を閉じる間もなく唇が触れ合った。
驚きに声を漏らす間もなく、は抵抗のために腕を振り上げたが、最初から彼に振りおろす気などあるはずがない。拒む理由が見当たらないまま腕は力なく下ろされる。
人通りが少ないとはいえ往来だということも忘れては平馬のシャツの背を掴んで瞼を下ろした。
息継ぎすら忘れてしまいそうな優しいキスの余韻に浸るように、は平馬の耳元で囁いた。
「これから少しずつ返すっていうのは?」
精一杯の気の利いた誘いかけのつもりであったが、平馬はを抱く手を離さずに低く掠れた声で呟いた。
「少しずつじゃ足りないし。大体七年分とこの先の分、これからきっちり返してもらわねーと」
そう言って拗ねたように外される視線にはまた、声をあげて笑った。
どうやら夜は長くなりそうだ。