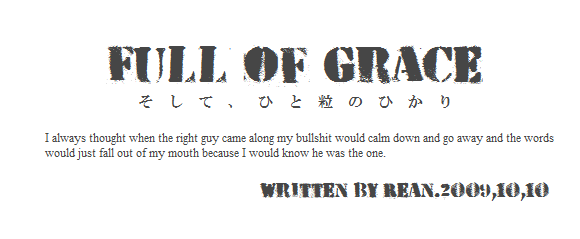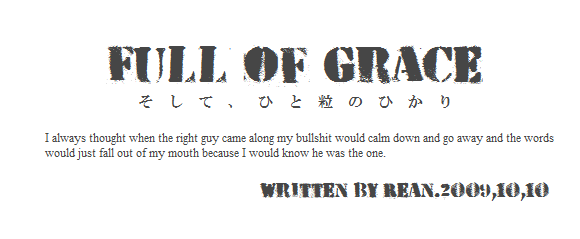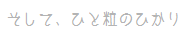
PLLLLLLLLL! PLLLLLLLL! PLLLLLLLL!
電話が鳴り響いた時、はまだベッドの中にいた。―・・・誰か、ふざけて巻き舌でもして唇を震わせてるの?・・・―だなんて。強い日差しから逃れるようにして、まるで夢見心地で横たわっていたが、やがていつまでたっても鳴りやまないしつこい音に痺れを切らし、は傍らにあった受話器に手を伸ばした。の部屋にある古びたの電話の不便なところは、携帯電話と違って相手が表示されないところだ。備え付けの電話のコードを切るわけにもいかず、そのまま受話器を手に取った。
「はい、」
口の中が乾いていて掠れた声しかこぼれない。乾いた唇を舌先で湿らせながらは瞼を指先で拭った。もしもし?―・・・確かめるように囁いた次の瞬間、鼓膜を震わせたのは聞き覚えのある関西訛りと呆れを含んだ声音だった。
『ちゃん、いつまで寝とんねん!』
耳元を擽る低い叱り声にはベッドに戻りながら寝ぼけた声を絞り出す。寝がえりをうちながらうつ伏せになり、足を折り曲げて獣のように身体を伸ばす。
「んー・・・今日って何かあった?」
『ちゃんのいけず。確かに、僕らなんも約束なんてしてへんけど、愛しの彼氏からの電話にそっけないで』
「寝起きだもの、許して」
『そりゃ勿論。けど、十一時まで寝とるなんて不健康と違う?』
「だぁって、夜通し遊んでたんだもん」
『・・・世の中が女の子に独り暮らしさせたないっていうてたわけがようやっとわかってきたわ』
「今更でしょう」
『よう言うわ。なぁちゃん、聞いてえな! 僕な―・・・』
は電話越しの恋人の話に付き合いながら、の片手はベッド横の灰皿の隣をまさぐる。お気に入りの煙草と安物のライターだ。煙草を一本取り出し火をつける。ベッドの上にある煙草の箱をまた机の上に放り投げながら息を吐く。空腹時の一服は肺に染みる。寝起きの不機嫌などとうに消えうせていたところで、安堵するように煙草を指先に挟むが指先から感触が消えた。
ふと、自分のベッドを影が覆っていることに気がついて顔を上げると、携帯電話を片手に笑う恋人の姿がある。驚くのも束の間、彼はベッドの端に腰を下ろす。彼のお気に入りだというパーカーのポケットに手を突っ込みながら、が問いかける間もなくにっこりと微笑んだ。
「久しぶりやね」
こんなもん吸ってたら健康に悪いで。なんて、まるで母親のような台詞を投げかけながら、彼はから取り上げた煙草を灰皿に押し込んだ。たちまち消えていく煙と、彼の顔とを視線が行き来したところで、の頭はやっとのことで現実を呑みこみはじめた。
唇にあてた指先の隙間を縫うようにして、無意識に言葉は零れ落ちていた。
「・・・どうしているの?サッカーは?」
目の前の彼は学生のような風貌をしているが押しも押されぬサッカー選手である。こちら、イタリアに留学してまでサッカーをしようというのだから、彼はかなりの実力者である。サッカーに明るくはないでも、海外でプレーすることの意味を良く知っているつもりだ。
「昨日からしばらくオフなんよ。どうせやったらちゃんを驚かしたろ思ってな」
確かには、彼にアパルトマンの合鍵を渡していたが、彼がこうしてやってきたことなど付き合い始めたころから一度としてなかった。
ゆえに、彼―・・・吉田光徳の突然の来訪にが驚くのも無理のないことだといえた。彼はそんなの驚きなど、まるで気にしていないのか、口元を綻ばせて優しく問いかけてくる。
「なぁ、驚いた?」
「とってもね」
はベッドから身を起して膝で立ちながら電話を置いて、ようやくベッドから降りた。その傍らにいた光徳の肩に腕を滑り込ませながら、猫のように甘く身をすりよせて彼を抱くと、より力強く抱き返される。身体を包む光徳の腕の心地よさを味わいながら、久しぶりに感じる日向のような匂いを確かめるように、彼の肩に顔を埋めながらは問う。
「コーヒー飲む?」
「ぼくカフェ・オレがええな」
「こっちじゃカフェ・ラテっていうのよ」
「どう違うねん」
すかさず入る関西特有の調子には小さく笑った。言葉の違いよ、なんて野暮なことは言わない。
彼の手を掴んで一緒にキッチンまで歩きながら、彼のために席を勧めてはコーヒーメーカーに豆を入れながらスイッチを押す。自ら豆を挽くほどに本格的なものではないからバールやカフェのような旨味は薄いが、それなりに舌を満足させるくらいの味は保証されている。冷蔵庫から取り出したミルクを鍋に入れて温めながら時計を見上げれば、もう十二時近くに針がある。これではもうランチの時間だ。は椅子に座ってこちらを楽しそうに眺めている光徳を振り返った。
「朝ご飯は? 食べてるわよね?」
「うん、」
「お昼は?」
「まだやねん。ぼくもうお腹ぺこぺこやで」
「じゃあ、電話越しにそっけなくしたお詫びに、お腹をすかせた光徳くんにご飯をつくりましょうか」
「おおきにー」
冷蔵庫を覗き込めば、とりあえず数日分の食材が確保してあることに安堵した。狭いアパルトマンだが使い勝手は良い。両手に昨日の残り物のタッパーとミネラルウォーターの瓶を取り出しながら、手のふさがったはいつものようにお尻で冷蔵庫を閉める。その一部始終を見ていた光徳は、微笑ましげに笑った。
「かわええなぁ」
光徳は、を可愛がるのがとても上手い。そうやって、柔らかな口調で可愛いなんて賞賛してくれるのは多分彼をおいて他にはいない。日本人のくせに素直な賞賛が上手く、例え彼の唇からこぼれる言葉たちがお世辞だとしたって褒められて嬉しくない女なんていないのだ。だとて例外ではない、頬にかかる髪を押し上げながら照れたように唇を尖らせる。
「やだ、見てないで手伝ってってば」
「ごめんな、つい見とれてしもうてん」
言うが早いか。光徳は机の上に散乱する楽譜の数々や学校の課題の設計図。食べかけのブラウニーや蓋をあけっぱなしだったペリエをすばやく片付けてくれる。ピアノの椅子の側にある簡素な段ボール箱の中に彼が勝手知ったるという雰囲気で仕舞ってくれるのを眺めて、は改めてその手際の良さに驚いた。けれども不意に、彼がベッドの上でのことを愛してくれる時の一連の手際の良さと符合する。何ら不思議のないことだと認めて、はとっさに俯いて思わず笑ってしまう。
几帳面、けれど時々不作法な意地悪をする。けれどそれすら愛おしい。それが彼。―・・・まだ昼だというのにこんなことを考えるなんて。
そんな昼間の不埒な思惑を掻き消すようにしてコーヒーメーカーが仕事を終えたことを告げてくれる。はコーヒーがたっぷりと入ったポットを引き上げながら温めていたミルクと合わせて光徳のリクエスト通りにカフェ・ラテを作る。は自分の分のブラックをいつも使っているカップに淹れたところで、二つのカップたちはあっという間に光徳の両手に攫われる。
「机の上、片付けといたで」
光徳の言葉通り、既にすっきりと片付けられている。昨日の食べかけのブラウニーもいつの間にか冷蔵庫の中に行儀よくラップにくるまっていた。カップを机の上に置きながら、は彼の頬にお礼を込めて口づける。
「ありがとう、お客さんなのに働かせてごめんね」
「ええのええの、だってぼくが勝手に押しかけてきたんやもの」
「でもオフでしょ? 休まなきゃ」
「だって落ち着かんのやもん。一人で家にいるよりちゃんと一緒にいたいんよ」
「誰にそんな言葉教わったの? チームメイト?」
イタリアーノのような手慣れた口調には思わず口元を緩めて笑いながら問うと、少しむくれた返答が返ってくる。
「なんや、つれへんの」
「だって、真に受けてたら身が持たないんだもの」
「でも相手がぼくのときはちゃんと応えてくれなあかんで?」
「はぁい」
はそっと腕を伸ばして、カフェ・ラテを飲み終えた彼の口元についたミルクの口ひげを指先で拭いながら頷いた。いつになくしおらしい、素直な返事に笑いあう。光徳は日本人だが、は彼といても日本にいる気が全くしない。現実感がないわけではなく、彼があまりにもこの街になじんでいる。どこにいてもなじむのだろう。こんなふうにいつだって彼は、を上の空にさせる。光徳と一緒にいる時ですら、は光徳のことを考えてしまう。彼がしたこと、してくれること、してきたことを頭の中でなぞり上げて少しだけ切ない想いに浸るのだ。
「なぁちゃん、何考えとったん?」
「光徳のこと思いだしてた」
「ぼく、ここにおんで?」
「私の前からひょっこりいなくなっても、困らないように訓練してたのよ」
はコーヒーを飲みながら砂糖を僅かにすくったスプーンで、心の中に何かを沈めるようにしてかき混ぜる。ふざけているわけではなかった。光徳はイタリアに根を張って生きるわけではないだろうが、それにいつでも会えるわけではない。電話越しなのが殆どで、今日みたいに会いに来てくれるなんてことは殆ど稀だ。そんな悟ったようなの様子に、光徳は眉を下げながら困ったように呟いた。
「そんなこと言われたら、ぼくの方こそ困ってしまうやん」
その呟きを拾ったは、わけもなく動揺した。予感があった。なんだろう。彼はいつも、何かあっても上手く流してしまうし、喧嘩になったこともなかった。けれども、抽象的なものではない。もっとなにかはっきりと形を持った―・・・
「ちゃんと話せぇへんとって思ってたんやけどな、」
「うん」
は取り落とさないようにカップをテーブルに置いて、光徳の話に耳を傾けた。彼はどうしてか、穏やかな声で告げてくる。
「ぼく、来シーズンは日本に帰ることにしてん」
「えっ・・・そう、なの」
「うん・・・残るかどうか悩んだんや。けどな、やっぱり、一度日本に戻ってみよう思ったんよ」
急な話だとは思ったが、それは単ににとって急であったというだけで、光徳にしてみれば随分前から悩んでいたことらしい。が彼を引きとめるすべはない。それくらいは、彼よりもほんの少し長く生きているからわかるのだ。
「私たち、もう会わない方がいいのかしら?」
「なんで?!」
「もう決めたんでしょう? なら、私のことも、中途半端にしないで」
連れて行ってならまだしも、置いて行ってなんて言うのはあまりに惨めだ。はもう光徳の目を見ていられず、俯いた。瞳に溜まった涙が俯いた拍子に霞がかって、ゆっくりとテーブルにしみをつくっていく。指先でこぼれ落ちる滴たちを拭いながら、は顔を上げられない。光徳が席を立つ。気配ですぐにわかった。身体を屈めて、彼はの額をかきわけてキスをすると、いつものような優しい口調で窺うように言うのだ。
「ごめん。ぼく、一旦帰るな。ごめんな、ちゃんのこと混乱させてしもうて」
私こそ―・・・そう言えたらどんなによかったろう。けれどは、みっともなく食い下がれない。遠ざかっていく足音に閉ざされた扉の音が耳に入ったところで、はバスルームに飛び込んで、シャワーのコックを捻って泣いた。
***
―・・・きみ、かっこええな。
不意には光徳と初めて出会った日のことを思い出した。音楽の勉強をするためにイタリアにやってきたはすぐにもアパルトマンを借りたこの街に魅了された。親からの仕送りだけでは食いつないでいくには難しく、は副業として夜のバールでピアノを弾くアルバイトをはじめたのだ。光徳に出会ったのは夜のバールでピアノを弾くのにも慣れ始めた日のことだった。
は生まれつきそれほど手が大きくはなく、ピアノを続けていくには不自由だと言われていた。ピアノにかけるのと同じくらいお洒落が好きで、そんな爪でピアノを弾くのかと何度揶揄されたか知れないが、それでもヒールを履くことも、爪に色をつけることもやめなかった。手で届く範囲が狭いと言われたら、ヒールを纏った片足を鍵盤に上げてアレンジをこなしたこともある。ちょうどその日も、そんな風に、ピアノと向かい合っていたに、曲が終わってしばらくしてから彼は声をかけてきたのだ。人懐っこそうな笑みを浮かべた彼は、日本語で話しかけてきてくれた。跳ねまわった黒髪と口元のほくろが印象的な男だった。かっこいいなんて賞賛を受けたことが初めてのは、しばらく驚いて彼の顔を見つめたのだが、やがてピアノの鍵を綺麗にしながら笑顔で応じた。
「かっこいいより、かわいいって言われた方が、嬉しいかな」
そして、の言葉に安堵したように微笑むのだ。それ以降、光徳はことあるごとにに可愛い可愛いと言ってくれるのだが、なるほどそれは喜ばせるために言ってくれていたのだろうか。
「あー、よかった! 日本語で話しかけてしもうたから、日本人やなかったらどないしよう思ったわ」
「関西の人?」
「そう、大阪。きみは?」
「東京」
「へぇ! ここで会うたのなんて奇跡やんなぁ」
底抜けに明るい彼の雰囲気は、まさに陽気なイタリアの気質と合っていては思わず唇を震わせた。《奇跡》なんて、人が起こしていくものだとたかをくくっていたリアリストの自分を殴りつけたくなった。そう、まさしく彼の言った通り奇跡だったのだ。
そしてこのささやかな出会いすらも奇跡だと言ってしまえる男に、思えばあの時から、は惹かれ始めていたのだろう。
だから、だめなのだ、こんな終わり方は。
***
シャワーを止めて、は弾かれたようにバスルームを飛び出した。光徳の足音が遠ざかっても、彼と過ごした記憶がの中からそう簡単に遠ざかるわけはない。こんな恋の終わり方ではだめだ。は玄関に転がっていた靴に足を通し、シャツとショートパンツだということもすっかり忘れてドアを開けた。
ドアを開いて駆け出そうとした瞬間に、ドア先に見知った後姿が座り込んでいる。
「あ、」
「ちゃん」
が何と声をかけるべきか迷っていると、彼―・・・光徳は立ちあがって足元の砂を払ってふにゃりと笑う。
「ぼくな、忘れ物してしもうて」
そんなとんちんかんな言い訳をしてここにいる方法を一体どこから学んでくるのだろう。頭の後ろに指を差し入れて照れ臭そうに笑うと、彼はドアの間に身体を滑り込ませながらに問う。
「なぁ、ぼくに会いに行こうとしてくれたん?」
は返事をしなかった。その代わりにその言葉を、声を鼓膜で転がすように、光徳のことを見つめて柔らかく微笑んだ。そんなの態度に、物足りなさをあらわにしながら、彼は囁く。
「ぼくはな、ちゃんとずっと一緒にいたいんやけど」
ただの口から、言葉を創り出させるために、光徳はの頬に触れながら瞳を撫でるように見つめてくる。なぁちゃん。彼の唇は言葉を紡ぐ。恋が創り上げて、口から押し出させる言葉。彼はそれを待っているのだ。にはわかった。けれども涙を浮かべた瞳で彼のことを見つめるだけだ。頬をすっぽりと覆う掌にが返事をするように唇で触れれば、観念したように光徳は呟く。
「やっぱり、ちゃんは大人やな」
「どこが?」
こんな駄々をこねるみたいに泣きながら、何も言わないなんて一つも大人のやり方ではないだろう。
「だって、“愛してる”なんてひとことも言わずに、ぼくにわからせるんやもの」