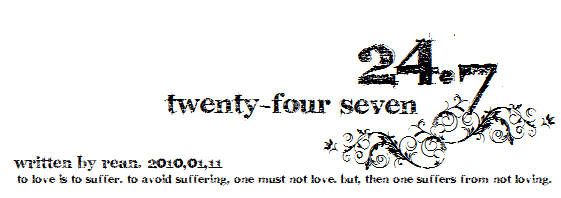私たちはどれくらい、こうして向き合っているんだろう。 はイリオンとお茶をしていた通りを抜けて、天城の前に立った。 立ったところまではよかったが、実際彼を前にしてしまうと何から伝えればいいのかわからない。 物書きゆえに、ある程度台詞の想定はできても、肝心な場面で何一つ大事なことが浮かんでこない。 「勝手なことしてごめんなさい」「拗ねてごめんね」「もしかして怒ってる?」が思いつく限りの謝罪の言葉は多岐にわたる。 けれども、そのどれもが本心からではない。口をついて出たのはもっと別の言葉だった。 「・・・なんでいるの?」 俯きがちに呟いた冷たい声に、天城が動揺を露わにすることはなかった。 まるで、こうなることが予めわかっていたかのように、慣れた手つきでの手から荷物を奪う。そしてしっかりとした口調で、彼は訊ねてくる。 「理由がいるか?」 荷物と共に、大事な台詞すら奪われてしまった気がする。ここ数日心を覆っていた苦いものたちを振り払うようにはひたすら首を振った。 「わかんない」 天城から視線を外して、は呟いた。 これ以上往来にいたら、口喧嘩を始めてしまいそうな気がしては踵を返す。自分のアパルトマンまでの近からずも遠からずの道のりを歩きはじめた。 途中でタクシーを拾わなかったのは隣同士になりながらも話題に詰まるような沈黙を味わうのが嫌だったからだ。 沈黙は嫌いではない。特に彼との間にある無言の空間は心地よくすらあった。その記憶を、嫌なものに塗り替えたくなかったからかもしれない。 はブーツのつま先で力強く石畳を蹴りながら天城を振り返ることなく歩き続けた。きっと彼はついてくる。 彼がの荷物を手にした時、既にそんな予感があった。例えるなら、ここ二週間近く連れて歩いた手荷物は天城のことをに繋ぎとめる枷となったのかもしれない。 どこに行こうとしているのか、何をしようとしているのか、の起こす行動の意味を天城が問うことはなかった。 ただ黙って、の後を追いながら近すぎず、遠すぎずの距離感を保っている。本気になれば、いつだってのことを捕えられる力を持っているはずなのに。 ヴァイナハテンの前夜と同じように、コートのポケットに収まった鍵で門をこじ開け、タイルの敷き詰められた階段を駆け上がる。 後ろから聞こえてくる足音の刻むリズムの数が耳に飛び込み、に天城が追ってきたことを報せる。後ろを振り返らなくてもわかる。 それは決して自惚れではない。開いたドアをすりぬけて部屋に入る私と、躊躇ったような気配の後に、ドアを支えて入って来る天城の気配がある。 彼は何も語らない。まるで、自分がそこに存在しないかのような振舞いにはいい加減に焦れてくる。 脱いだコートをベッドの上に放り投げ、ブーツのジッパーを下ろし、ついでにシャツのボタンを外す。苛立ちを込めて髪を掻きあげた。 不機嫌のあまりシガレットケースからシガレットを抜き去って火をつける。吸い口に唇を押し当て、細い煙が咥内に充満するのを感じながら白い息を吐き出す。 スポーツ選手の前で煙草を吸うなど好ましいことではないとわかっているのにこんなことをしているなんておかしい。 いつもの自分ではない。優しさや思いやりを忘れた行為に再びの自己嫌悪に襲われながらシガレットを灰皿にねじ込んだ。 腹立たしさを紛らわすように額を抑え込みながら、は天城を振り返った。 を見つめる彼の瞳は、数ヶ月前にに見せたそれと何ら変わりはない。怒りもなく、同情もなかった。ただ彼はを視ていた。それで十分だった。 出来ることなら、今すぐに駆け寄りたいと思った。けれどそれでは何の意味もない。 自分こそ、この数週間のばかばかしい出来ごとにけじめをつけなければならないはずであった。 二人の間にはただ静かな沈黙が流れていた。どれくらい互いを見つめあっていたのだろうか。 「うんざりしたでしょ? 我儘で、自分のことしか考えてない私に、」 「正直なところ、わからない。でも傷つける原因は俺だった、違うか?」 「ううん・・・違うと思う。いつもならね、『あーそう、ストじゃしょうがないよね』で流したと思う。でもいつもならとれる大人な態度がとれなかったの」 「そうか」 天城は、聞き流すわけでも否定するわけでもなくただ頷いてくれた。 「ね、燎一。これってどういう意味だかわかる?」 「どういう意味って?」 「私が、子供に戻ったみたいにだだこねて、ヴァイナハテンは一緒がよかったの! って拗ねる意味よ」 あまりに唐突なの問いかけに、天城は首を捻った。わからないだろう。 リビングの上に置き去りにされたグラスや皿、シンクに放り出した料理たちの意味をきっと彼は知らないだろう。 知られたい、報せてやりたいと思う自分がいる一方で、そんなばかばかしいことを悟ってもらっても意味がないことをはもう知っている。 ふと思い浮かんだ懐かしいフレーズ、あなたといたい24・7。 そうだ、私は、燎一と離れたくなかったんだ。 今更ながらに自分が思い至った理由があまりにも単純で、それでいて恥ずかしげもない明瞭さには苦笑をこぼす。 「何がおかしい?」 「ううん。自分でもよくわかってなくて、でもあまりにも単純なことでおかしくなっちゃった」 まだドアの側で所在無げに立っている天城の手を引いて部屋に招き入れる。 シンクの上に取り残された食器たちに気付かせないように瞳を反らすことはなかった。 「ごめんね。駄々こねて、こじれさせて、本当にごめんなさい」 「いや、本当のところ少し嬉しかったんだ。いつも俺の言うことに頷いてばかりで、辛い思いばかりさせてるんじゃないかって思ってたから」 照れ隠しのように、天城は屈んでを優しく抱きしめながら囁いてくれる。 懐かしい彼の香りを貪るように強く息を吸い込んだ。忘れかけていた温度を味わうように天城の首に腕を回すと強く腰を引かれて抱きしめられる。 腰を抱く彼の掌の大きさに無意識に胸を高鳴らせながら問いかけた。 「許してくれる?」 「俺こそ、悪かった」 ぎこちなく、鼻先を寄せて唇を触れ合せる。 ほどけかけた結び目が、再び強く繋がっていくのを心のどこかで感じている。きっとそれはお互いに。 解放を求めてせりあがっていた気持ちがいつの間にかなくなっている、彼の瞳を見つめることすらあれほどもどかしかったというのにだ。 きっとどこかに昇華されていったのだろう。は天城に強く手繰り寄せられていくのを感じながら瞳を閉じた―・・・。 *** ヴァイナハテンの夜は、ご飯も、シャンパンも、シュトレンもあって完璧だったのに、天城がいなかった。 今夜は天城が側にいてくれるのに、まともな食材がない。けれど、心は酷く満たされていくのを感じていた。 外れかかった歯車が再び強くかみ合って動き出すのを感じ、はベッドを抜けて遅い夜食を作るべく冷蔵庫の中身を漁った。 ところが目ぼしい食材は殆どなく・・・思えば今日まで家に帰っていなかったのだった・・・生憎と、手をつけてはいなかったシャンパンやワインとチーズくらいしかない。 シュトレンの方は箱を開けてみたら既に砂糖が溶けかかって心なしかしっとりとしている。多分中ると感じてすぐさまダストボックスへと突っ込んだ。 チルドにあった余った野菜たちといつかの朝食用にとっておいたヴルストを取り出しながらは食材を刻んで鍋へと放り込む。ポトフくらいは作れそうだった。 鍋の蓋を閉めてシンクに寄りかかったところで留守番電話の存在を報せるランプがその存在を強く訴えかけてくる。 両親たちと年を越したこともあってか、忘れ物か何かの連絡だろうか、は最初の伝言を聞いて無意識に呟いた。―・・・「嘘だ。なんで、」 それは所在無さげな天城の声と共に始まった。 『悪かった、パリから列車に乗ればすぐなのに気付かなかった・・・』 延々と続いた懺悔の台詞と共に一件目の電話は切れる。 『もしかして、パリからかけた電話で聞いたことに怒ってるのか?』 二件目。 『アパルトマンの傍まで来たんだが留守にしてるのか?』 三件目。 『今どこにいる? この留守電聞いたら電話でもメールでも、連絡をくれないか?』 四件目。 『俺が悪かった。俺が言うのも変だが、その・・・どこかに行ってしまわないでくれ』 五件目。 様々なメッセージは一昨日まで延々と続いていた。 不器用な天城は肝心なことを滅多に話してくれない。 としては既にそんなことには慣れっこだし、不安に感じる要素でもないが、饒舌に語る過去の天城からのメッセージに自然と唇が震える。 泣き出しそうなほどに張り詰めた感情を抑えつけるように指を握りしめ、はとうとうしゃがみこんだ。 冷たいフローリングの上に膝をつきながらメッセージを消去できないまま、指先は行き場を失って虚空を掻いた。 嗚咽を零さないよう、口元を抑え込みながら呻くと、不意に大きな掌がシャツ越しの肩を撫でるように触れる。 びくりと肩を揺らすと、後ろから抱き締めるように身体を引きあげられて、は泣き声交じりに囁いた。 「りょういち?」 「聞いたのか?」 しきりに頷きながら、は甘えるように天城に抱きつく。 彼は困ったように、というよりばつの悪そうな・・・まるで悪戯が見つかった子供のような心もとない表情で力なく笑って見せた。 「消してよかったんだぞ?」 「ううん、本当、ごめんなさい」 「謝るなよ。これからそんな風に謝られたら困る」 「これから?」 「ああ、そうだ」 の問いかけに明確な答えはなかった。ただ天城はから離れ、フローリングの床に片膝を落とす。そうして壊れ物を扱うかのような丁寧な仕草での左手を取った。 「本当は、ヴァイナハテンで言うつもりだったんだ」 「え、やだこれって・・・」 うわごとのように口走ったに天城は黙るように視線で促しながら、彼女の左手の指先に触れた。 「結婚してほしい、さん。君を愛してる」 差し出された小さな箱にはまろやかなラインの指輪がある。溜息が出るほど美しいその輝きに、は震える吐息を零す。 暗闇の中、目を凝らせば天城の指にはもう、シルバーの指輪が収まっている。迷っている時間など必要なかった。 緊張に張り詰めた空気を破り捨てるように、は跪く天城の腕に飛び込んだ。 はい、Yes、ouiあるいはJa、この世のどんな気の利いた返事よりもの仕草は雄弁に愛を語る。 二人して安堵の吐息を零し、耳まで赤い天城をがからかえば、仕返しとばかりに唇に噛みつかれる。 数か月ぶりに心を通じ合わせる恋人同士が夜中だというのに堪え切れない熱を溢れさせながらじゃれ合う。 フローリングの床に横たわり、唇を啄ばむように触れ合わせれば自然と愛しさが肌に滲みだす。 それを伝えようときつく掌を重ね合わせ、互いを恋しがる温度を知りたがるように触れ合う。24・7/twenty-four seven、いつでも、あなたといたい二十四時間。これからはあなたといられる、あなたの心に寄り添う二十四時間になる。 勿論誰も咎める者などいるはずがない。 先ほど火にかけた鍋のポトフが、噴きこぼれる以外には。
|